社会保険・労働保険の手続きは、年・月・スポットの波が大きく、ひとり所長の事務所では「業務の平準化」と「ミスゼロ運用」が常に課題になります。算定基礎・月変・年末調整・36協定・労災手続きに加え、マイナンバー管理や電子申請、公文書の取得・保管まで含めると、Excelやメールだけの運用では限界が見えやすくなります。
このギャップを埋めるための手段が、社労士向けソフトの導入です。目的は大きく「手続きの一元管理」「電子申請の安定化」「ミスを防ぐ仕組み化」「顧問先との情報授受の効率化」「監査対応を見据えた証跡管理」の5点に集約されます。費用は“単なるコスト”ではなく、作業時間・やり直し・見落とし防止のリターンで回収する投資と捉えるのがポイントです。
一方で、ソフト選定は「何ができるか」だけでなく、「いくらで、どの規模まで無理なく運べるか」を軸に考える必要があります。とくに開業〜顧問先30社までのひとり所長では、月額費用に加えて“顧問先枠”や“利用ID数”、オプション有無、既存の給与・勤怠との連携コスト、切替の手間も実質コストとして効いてきます。ここを見誤ると、導入後すぐのプラン変更や運用の行き詰まりを招きがちです。
本記事では、こうした観点を踏まえつつ、オフィスステーションProを単独で掘り下げます。電子申請を核に、顧問先情報の集約、マイナンバーや公文書の管理、年次イベントの平準化までを、ひとり所長の実務フローに合わせてどこまで任せられるかを検討します。また、顧問先数(〜30社)×ID数を主な判断軸に、費用と運用負荷のバランスを具体的に見ていきます。
このあと、まずはProの全体像と最新の料金体系を確認し、続いて「顧問先数・ID数・年末調整の有無」で分岐するおすすめ構成を提示します。最後に、導入パターン別の概算試算と、電子証明書・委任設計・権限まわりでつまずかないためのチェックリストもご用意します。読み終えるころには、「自事務所の規模・方針なら、どの構成が最短距離か」がクリアになるはずです。
社労士ソフトとは?
社労士ソフトとは、社会保険労務士が担う多様な業務を正確かつ効率的に進めるためのクラウド型業務支援システムです。就業規則の作成・届出、社会保険・労働保険の各種手続き、労使協定や労災関連帳票の作成、年次イベント(算定基礎・月額変更・年末調整)までを一元管理し、電子申請や公文書の取得・保管までをシームレスに行えることが特長です。
また、顧問先との情報授受を効率化するためのポータル機能、マイナンバーや個人情報を安全に扱うための権限管理・ログ管理、給与・勤怠・会計ソフトとのデータ連携、タスク/進捗管理やワークフロー承認など、継続的な顧問業務を円滑にする機能が充実しています。ひとり所長〜小規模事務所でもスケールしやすく、作業の平準化とミス防止、証跡の可視化に役立つのが社労士ソフトの役割です。
社労士ソフトでできること
社労士が扱う労務業務を包括的にサポートするクラウド型システムです。社会保険・雇用保険等の電子申請、毎月・年次の給与計算、顧問先とのデータ連携、案件ごとの進捗管理を中核に、台帳整備から帳票作成、公文書の保管・共有、報酬請求までを一元化します。ひとり所長でも運用しやすいワークフローと権限設計により、ミス防止と作業の平準化を実現します。
| 機能 | できること |
|---|---|
| 電子申請対応 | 社会保険・雇用保険・労働保険などの各種届出にe-Govやマイナポータル経由で対応。複数事業所の申請履歴を横断管理し、送受信記録や公文書の一括ダウンロード、印刷提出との切替にも対応します。 |
| 顧客情報・台帳管理 | 事業所・被保険者・家族情報・資格履歴などを一元管理。変更点は申請フォームへ自動差し込みでき、退職・異動・住所変更などのイベントも履歴で追跡可能です。 |
| 給与計算 | 勤怠データの取り込み、社会保険料・雇用保険料の自動計算、賞与計算、控除項目の設定に対応。賃金台帳・給与明細の出力や外部給与ソフトへの連携も可能です。 |
| 顧問先とのデータ共有 | 依頼・承認・資料提出をポータルでやり取り。雇用契約書や入退社情報、マイナンバー等の機微情報も権限・ログ付きで安全に授受し、未提出アラートや催促の自動化に対応します。 |
| 手続進捗管理 | 案件ごとに担当・期限・ステータスを可視化。算定・月変・年末調整・36協定などの定期タスクをテンプレ化し、漏れ検知やリマインド、完了後の公文書格納までをワンフロー化します。 |
| 労災給付手続き | 様式作成を支援し、療養補償・休業補償等の必要情報を台帳から差し込み。事業主証明や医療機関書類との整合チェック、公文書控えの保管・共有にも対応します。 |
| 労働保険個別申告 | 年度更新や有期事業の申告に必要な賃金集計を自動化。概算・確定の計算、申告書生成、電子申請または印刷提出の選択、納付書控えの管理まで一気通貫で行えます。 |
| 報酬請求管理 | 顧問料・スポット料の請求書発行、入金消込、未収アラート、案件別の原価・作業時間の記録に対応。月次請求の自動化や会計ソフトとの仕訳連携も可能です。 |
オフィスステーション Pro(株式会社エフアンドエム)

オフィスステーション Proは、社労士事務所向けに設計されたクラウド型の労務管理システムです。導入事務所数は3,000以上とされ、e-GovのAPI申請や健保組合の電子申請、入社手続きからマイナンバー管理までをワンストップで効率化します。CSVやAPIを通じて他社の給与・勤怠システムと連携できる点も特長です。電子申請の対応帳票は公称158種類で、主要手続きをシステム内で完結できます。公文書は自動反映機能などで台帳へ取り込み、顧問先への送付運用も支援します。ひとり所長〜少人数体制でも、案件・拠点をまたいだ申請状況の共有と業務分担をスムーズに進められるのが強みです。
オフィスステーション Pro | 年間200時間の業務改善を実現!
この記事のゴール(誰に向く?どこでProを選ぶ?)
本記事は「開業〜顧問先30社までのひとり所長」を主読者として、費用×顧問先数×ID数の観点から、オフィスステーション Proの最短解を示します。電子申請を中核に据えつつ、年次イベント(算定・月変・年末調整)やマイナンバー、公文書管理をどこまで任せられるかを確認し、「いつライトで十分か/どこからスタンダードに上げるか」の判断軸を明確化します。
オフィスステーションProの全体像
対象:社労士事務所(ひとり所長〜少人数)
Proは社労士向けのクラウド製品で、ひとり所長〜小規模体制での運用を想定した画面設計とサポート体制が特徴です。入退社の初期手続きから、マイナンバー収集・管理、電子申請、公文書の取得・共有までをワンフロー化し、顧問先とのやり取りをポータルで簡素化します。
対応範囲:e-Gov API/健保組合対応/労災帳票(24種)など
e-Govで提供されるAPI申請に幅広く対応し、主要健保組合向けの電子申請や、労災関連帳票の作成(24種)にも対応します。台帳データの自動差し込みや、公文書の受け取り・保管の一元化により、アナログ混在のムダ手間を圧縮します。
料金とプラン(2025年版の一次情報)
ライト(11,000円/月・登録料110,000円/ID1・顧問先20枠)
- 月額:11,000円
- 登録料:110,000円
- 利用者ID:1/顧問先登録枠:20
- 枠・IDの追加が必要になった場合はスタンダードへ変更
スタンダード(16,500円/月・登録料220,000円)
- 月額:16,500円
- 登録料:220,000円
- 事務所の規模拡大・複数ID運用・顧問先枠拡大に適合
よくあるオプション(事務組合オプション等の実例)
事務組合を複数扱うケースでは、追加費用の設定がある資料も流通しています(見本市資料等)。導入前に自事務所の取り扱い件数や運用方針に合わせて確認しておくと安全です。
費用×顧問先数での分岐ロジック
〜20社・ID1ならライトで十分
開業〜20社規模で、事務所の利用者がひとり(ID1)で回せる前提ならライトが最適。初期費用・月額ともに抑えつつ、電子申請中心の運用を確保できます。
21社以上/複数IDが必要ならスタンダードへ(顧問先枠追加はスタンダードに変更)
顧問先が21社を超える、または複数ID運用が必要になった時点でスタンダードへ。ライトは枠・IDの追加が不可のため、余裕を持った早めの移行判断が実務的です。
“費用×顧問先数”おすすめ分岐(要点)
- 〜20社 & 利用者ID=1 → ライト(11,000円/月、登録料110,000円)
- 21〜30社 もしくは ID>1 → スタンダード(16,500円/月、登録料220,000円)
※ライトは顧問先枠・IDの追加が不可。拡張はスタンダードへ移行。
導入パターン別の試算(開業〜30社の“ひとり所長”向け)
| ケース | 前提 | 初期費用(登録料) | 月額 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| A:顧問先10社・電子申請中心 | ID1/枠20以内 | 110,000円(ライト) | 11,000円 | 開業初期の標準。年次イベントはテンプレ化して漏れ防止。 |
| B:顧問先20社・年末調整も併用 | ID1/枠20ちょうど | 110,000円(ライト) | 11,000円 | ライトの上限に達するため、増員・拠点追加前に移行計画を。 |
| C:顧問先25〜30社・ID追加ニーズ | ID2以上/枠拡張 | 220,000円(スタンダード) | 16,500円 | ライトでは枠・ID追加不可。迷ったら早めにスタンダードへ。 |
※上記は2025年時点の公表条件をもとにした概算イメージです。キャンペーン・個別見積で変動する場合があります。
運用イメージ(実務フロー)
顧問先データ収集→マイナンバー管理→API電子申請→公文書取得の一連(e-Gov APIの前提)
- 顧問先データ収集:事業所・従業員台帳を整備。CSV取込で初期登録を短時間化。
- マイナンバー管理:収集・保管・利用履歴を一元管理。申請様式に自動差し込み。
- API電子申請:対象手続を選択し、到達・審査状況を照会。必要に応じて電子納付の情報も取得。
- 公文書取得・共有:発出公文書を受領し、台帳へ格納。顧問先の受信ボックスへ送付して既読管理。
よくあるつまずき&回避策(電子証明書・委任状・権限設計)
- 電子証明書の期限切れ:年次イベント前に有効期限を棚卸し。更新リマインドをタスク化。
- 委任・権限の抜け:gBizID/委任関係の設計を初期導入で確定。拠点追加やID追加時に再確認。
- 台帳と手続きの不整合:台帳更新→申請様式差し込み→申請後の自動更新、までをルール化。
- 顧問先側の資料遅延:ポータルでの提出依頼テンプレと自動催促を活用。提出状況を一覧で可視化。
まとめ(この条件なら即“買い”、この条件なら再検討)
- 即“買い”:顧問先〜20社、ID1で電子申請中心。まずはライトで固定費を抑え、運用を固める。
- 移行検討:顧問先21社超、あるいはID追加・テレワーク複数運用を見込む場合はスタンダードへ。
- 導入前チェック:事務組合の扱い有無、年末調整・給与連携の要否、他システム連携(CSV/API)、証跡保存方針。
次回は日本シャルフさんです。
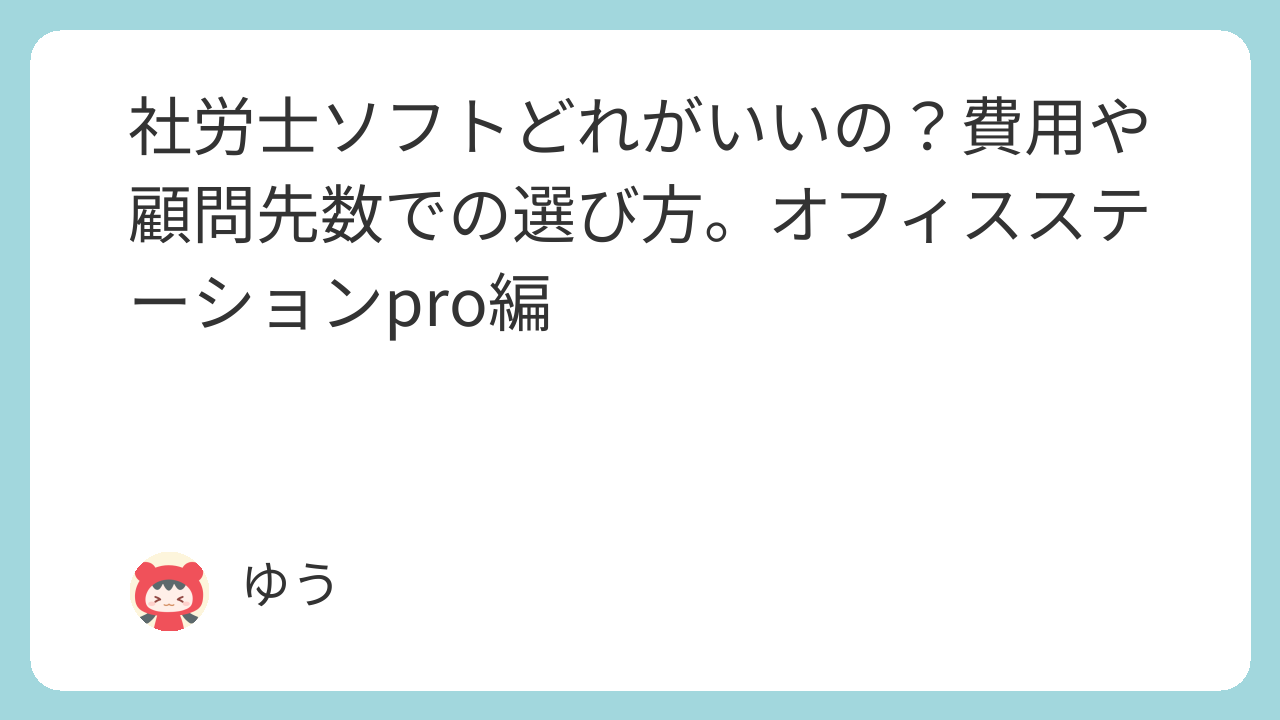

コメント